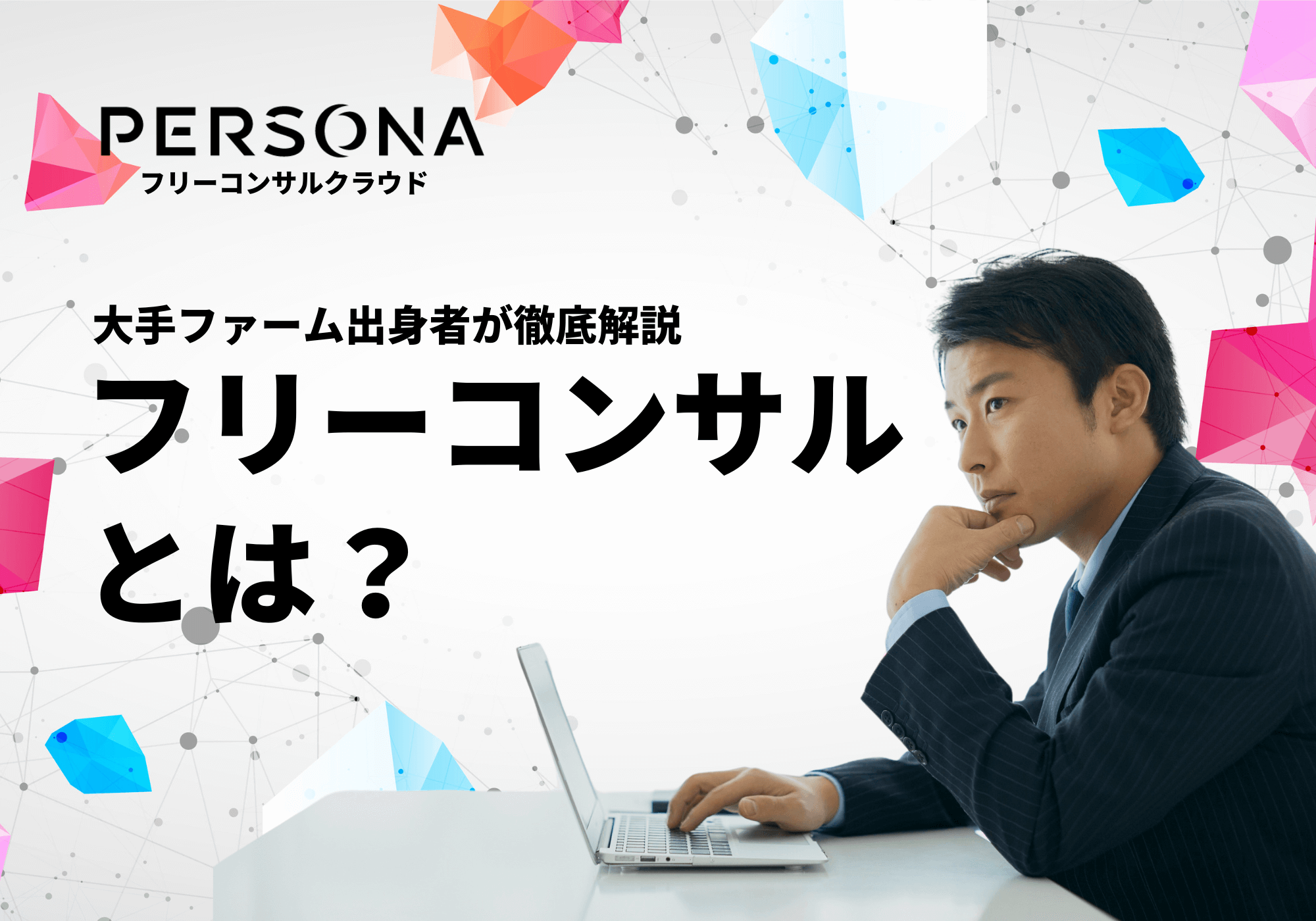「最近、フリーコンサルってよく聞くけど、普通のコンサルタントと何が違うの?」
「フリーランスのコンサルタントってどんな働き方をしているの?」
「年収はどれくらい稼げるものなの?」
そんな疑問をお持ちの方へ、今回はフリーコンサルという働き方について、大手コンサルティングファーム出身者の視点で詳しくまとめてみました。
この記事を読んでいただいてる方は、現在おそらく大手のコンサルティングファームにお勤めの方かと思いますが、転職しようか独立しようか悩んでいたり、あるいは独立しようとしていても、その後実際にどのようなフリーコンサル人生が待っているか心配だなと言う方に関して非常に有用な記事になっていると思いますので、ぜひともご覧いただけますと幸いです。
フリーコンサルとは

フリーコンサルとは、フリーランスのコンサルタントの略称
「フリーコンサル」とは、フリーランスで活動するコンサルタントを指す言葉です。一般的なフリーランスと同様に、会社員ではなく個人事業主や法人代表という立場で企業と契約を結び、コンサルティング業務を提供しています。
通常のコンサルタントとの違い
大手コンサルティングファームやいわゆる戦略ファームに在籍しているコンサルタントとの大きな違いは“雇用形態”です。大手のコンサルティングファームに勤めている正社員の方々は、毎月お給料が支払われる正社員の雇用契約となります。一方で、フリーコンサルは準委任による業務委託契約になります。
フリーコンサルは企業に所属しているわけではないため、
- 報酬が固定給ではなく、プロジェクト単位や稼働率に応じた支払い
- 案件獲得から契約、経理まで自ら管理する必要がある
といった特徴があります。
ですので、フリーコンサルは、報酬としては高額ではあるものの案件にたどり着けなければ、収入がなくなると言うデメリットもありますし、さらに経理対応などを自分でする必要があると言う点も手間がかかると言うデメリットの1つかと思います。一方で、働き方の自由さや報酬の高さを考慮すると、非常に悪の良い仕事の1つである事は間違いありません。
なお、提供するコンサルティング業務の内容自体は、コンサルティングファームに所属していた時と大きく変わらないケースが多いです。
例えば、戦略系のプロジェクトに現在従事されている方は、引き続き同じようなプロジェクトを同じように。システムPMOのプロジェクトにアサインされている方は、同じような形でプロジェクトデリバリーすることになります。よって、コンサルタントとして実施することはコンサルティングファーム時代と同様なのです。
では、フリーコンサルの実際の仕事内容や案件、働き方を次の章で見ていきましょう。
フリーコンサルの仕事内容と働き方

コンサルティング業務の本質は変わらない
先述の通り、フリーコンサルが行う仕事内容は、基本的には通常のコンサルタントと変わりません。戦略策定、事業計画立案、業務効率化、IT導入支援、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)など、多岐にわたります。
フリーコンサルの案件の種類(戦略系、業務系、システム系)の違い
コンサル案件には、(もちろん一概には言えませんが)大きく分けて「戦略系」「業務系」と「システム系」があります。
- 戦略系:中期経営計画の策定、事業戦略立案、新規事業開発などが中心。比較的、リモートでの稼働が許容される案件も多く、50%稼働(週2~3日稼働程度)など柔軟なアサインの仕方も見られる。
- 業務系:バックオフィス等のBPR(業務効率化)などが中心。リモートではなく、稼働の半分程度は現場での業務を求められる。80%~100%稼働(週4~5日稼働程度)など
- システム系:システム導入、要件定義、PMOなどが中心。100%稼働(週5日フル稼働)の案件が多く、常駐を求められることもある。
このように見ると、やはり、コンサルティングファームが実施している案件と同じような案件の種類であると言えるのです。
フリーコンサルのリモートワークの可否
コロナ禍を経て一時期リモート案件は増加しましたが、コロナ収束後は再び「常駐」を条件とする企業も少なくありません。
特にシステム系は関与するステークホルダーが多い中でフリーコンサルの人材だけ現場に出ないというのは確かに違和感がありプロジェクトとして非効率であるため出社を求められるのは自然な流れかもしれません。
加えて業務系においても現場の業務を実際に確認する必要があるためその点においても、現地に出社をするというのはこちらも必須であると言えます。
- 戦略系:フルリモート案件が比較的多い
- 業務系:一部現場での業務(主に業務視察・把握)が多い
- システム系:対面常駐を望まれる場合が多い
とはいえ、リモート主体のプロジェクトも一定数存在するため、介護や育児、地方在住などの状況下でも働きやすいのがフリーコンサルの強みといえます。
一般的な戦略案件であったり調査系の案件であれば、基本的にはリモートでこなせる案件が多いでしょう。(一方でコロナが終わり、戦略系の案件であっても週に1回程度出社してねという案件も増えては来ています。)
フリーコンサルの案件・報酬・稼働率

報酬の仕組み
フリーコンサルの報酬は、「高単価であること」かつ「稼働した分だけもらえる」というのが最も大きな特徴です。会社員のように毎月決まった給料が振り込まれるのではなく、プロジェクトごと、あるいは月ごとに稼働率を掛け合わせて計算されます。
例えば1人月あたりの単価が100万円の場合稼働率が100%か50%かにおいては、月に50万円程度も異なってきます。
- 例1:1人月100万円×稼働率100%=月100万円
- 例2:1人月100万円×稼働率50%=月50万円
相場感とランク
フリーコンサルの単価は、コンサルタントのランクや経験、出身ファームなどにより左右されます。
それでもBig4以上の大手コンサルティングファームの出身者であれば月に100万円を下回ることはないでしょう。
これはあくまで相場でしかないのですが、これを外れると案件受注の角度がかなり大きく下がるという印象です。
- スタッフ~シニアコンサルタント相当:月100万~120万円前後
- マネージャークラス:月150万円前後が一般的
- シニアマネージャー以上:200万円を超える案件もあるが、かなり特殊なケースか直接契約の場合が多い
稼働率の考え方
コンサル案件の稼働率は、1日8時間×週5日×4週=160時間/月を100%として考えることが一般的です。たとえば、
- 80時間/月(週2~3日勤務)だと稼働率50%
- 160時間/月(週5日フルタイム)だと稼働率100%
このように案件ごとに調整できるので、起業や副業と両立したい、育児や介護とのバランスを取りたいといったケースにも柔軟に対応しやすい働き方です。
なぜフリーコンサルは高単価なのか

フリーコンサルの報酬がなぜ高単価なのかというと、やはりコンサルタントのプロフェッショナルスキルが市場価値として高いということ、そして業界や職種における専門性がクライアントである事業会社にとってはとても希少価値が高いということに起因するかと思います。
よって、コンサルティングファーム出身者においても経歴にエッジが立っていなかったり、コンサルティングファームの在籍年数が3年を満たさない場合には案件を受注できなかったり、高い報酬でアサインしてもらえないなどの事態が起こりえます。
メリットとリスク
よって、コンサルティングファーム出身者にとってフリーコンサルになることは、高い報酬が設定可能であったり、柔軟な働き方ができたり上司や会社ルールへの対応が不要となる点がメリットであります。
一方でデメリットとしてはやはりフリーランスであれ以上収入は不安定となります。稼働しなければ収入を得ることはなくなり、案件獲得や税務処理なども全て自身でやる必要が出てきてしまうのです。また直接的ではありませんが例えば住宅ローンなどを組むにしても、会社員時代の方が容易であると言えます。
- メリット:高い報酬設定が可能、柔軟な働き方ができる、上司やファームルールなどの制約が少ない
- デメリット:稼働しなければ無収入、案件獲得や税務など自己管理が必要、信用力を得づらい(住宅ローンなど)
フリーコンサルになるのはどんな人?

コンサルティングファーム出身者が多い理由
フリーコンサルとして活躍している人のほとんどが、大手コンサルティングファーム出身者です。これは、クライアント企業が「ファーム出身の資料作成力やロジカルシンキング、課題解決力」を高く評価しているからです。さらに、ファーム在籍中に習得した業界知識・プロジェクト経験が重要なアピールポイントになります。
またコンサルティングファーム出身でなくても、コンサルティング自体は誰でもできるため、案件を受注することができなくはないと言えますが、一般的に業界慣習としてコンサルティングファーム出身者ということが前提になっているかと思います。
資格の有無
コンサルタントに関わる公的資格としては中小企業診断士などがありますが、大手ファーム出身のコンサルタントで必須とされていることはあまりありません。フリーコンサルとして評価される要素は、在籍ファーム・経験年数・担当プロジェクトの種類や規模などが中心です。
ブティックファームや大手ファームとの協業
フリーコンサルが活躍する場面として、事業会社直の案件と同様に、ファームが受注した案件にチームメンバーとして参画するケースもあります。大手だけでなく、ブティックファーム(創業間もない小規模ファーム)の案件にアサインされることも増えてきています。
ですので、アサインされる先としては、コンサルティングファーム時代と同様に事業会社の案件もあれば、コンサルティングファームのメンバーとして参画する案件(アンダーと呼ばれます)、加えて、コンサルティングファームの中でもブティックファームの案件というところに大きく大別されるかと思います。
一方で、ベンチャーなどの案件に関してはメガベンチャー以外はほとんどありません。これはフリーコンサルの単価が、大手のコンサルティングファームほどではないにしても高単価であるため、ベンチャーの資金力だと耐えられないというところが起因しています。
フリーコンサルの働き方
1. 完全独立型
100%フリーランスとして独立し、複数の案件を回しながら働くスタイル。目的は「収入の最大化」「柔軟な働き方」など。
フリーコンサルの報酬は非常に高く、また、稼働の調整もしやすいので、ファームの経験を活かした上で、理想の生活を追い求める人も少なくありません。
2. ハイブリッド型(副業・複業型)
意外に多いのはこのカテゴリの方。起業したばかりで、本業だけではまだキャッシュが不足している自身の事業を育てる傍ら、50%などの稼働でフリー案件に参画し、収入を補填という方も非常に多いです。
会社員のように100%稼動ではなく、50%稼動でも対応できるのがフリーコンサルの良いところですね。
このように、ライフステージや目指す方向性に応じた多様な働き方が存在しています。
案件の獲得方法とエージェント活用

人脈経由
コンサルタント同士のネットワークは非常に強力です。以前の同僚、上司、クライアントなどのつながりから案件を獲得する例が少なくありません。こうした人脈経由のプロジェクトは、相互理解がある分スムーズに進めやすいメリットがあります。
エージェントの活用
フリーコンサル専用の案件紹介エージェントも多数存在します。転職エージェントと似た仕組みで、希望条件や得意分野を登録し、マッチする案件を紹介してもらう流れです。
- ファーム出身者が運営・マッチングを行っているエージェントを選ぶと、案件やスキルを的確に見極めてくれる場合が多い
案件紹介の質
エージェントによって「戦略系に強い」「IT系に強い」「ファーム経営者がバックにいる」など特徴はあるものの、実際は多くのエージェントが幅広い案件を扱っていることが多いです。そのため、エージェントがどのような視点でマッチングしてくれるかが重要になります。
フリーコンサルとして案件を獲得するために重要なポイント

クライアントは「何をもってスキルを判断するか」
フリーランスのコンサルタントとして活動する上で、クライアントが何をもってスキルを判断するかは非常に重要なポイントです。基本的には、
- 出身ファーム(例:戦略系・総合系)
- 在籍年数
- 配属されていたユニット
- 担当していたプロジェクトの内容
といった職歴情報が第一の判断材料となります。
職歴以外に重視される「職務経歴書の内容」
それに加えて、職歴だけでは見えない部分を評価するために、クライアントは職務経歴書を重視します。実際に受注判断の際、以下のポイントが重要になります。
- どのプロジェクトに関与していたのか
- そのプロジェクトの課題・背景は何だったのか
- その中での自身の役割(ロール)は何だったのか
- どのようなアクションをとり、どのような価値(バリュー)を提供したのか
特に「スタッフとしての参画」だったのか「マネージャーとしてプロマネを担当したのか」といった立ち位置の違いも、発注判断の材料になります。
案件参画までの一般的な流れ

フリーコンサルが実際に案件に参画するまでのプロセスは以下の通りです。
- 案件にエントリーする
- クライアント側で「職務経歴書」「報酬金額」「稼働率」などを元に選考
- 面談オファーが届く
- オンライン面談を実施(これまでの職歴や経験が問われる)
- 案件オファーの有無が決まる
- オファー承諾後、案件参画へ
このプロセスの中でも、最初の「エントリー」に進むためには、適切なエージェントを活用することが非常に効果的です。
フリーコンサルの市場動向

フリーコンサルになりたいファーム出身者は増加傾向
フリーランス向けの案件紹介エージェントに登録することで、より多くの案件にアクセスできるようになります。実際、フリーコンサル市場は近年拡大傾向にあり、その背景には以下のような要因があります。
- コンサルティングファーム自体の拡大(特にビッグフォーなど)
- 退職者数の増加(=供給人材の増加)
- 独立する人材の増加(周囲のフリーコンサル事例を見て、自身も独立)
企業側もフリーランスを求めている
一方で企業側も、
- 採用がうまくいかない
- 専門性の高い人材を一時的に確保したい
- 市場にタレントが少ないため、フリーでの活用が必須
といった課題から、フリーランスの活用を積極的に進めるケースが増えています。
フリーコンサルになるための準備

経験・スキルの蓄積
ファームに1年しかいなかった場合、案件獲得の難易度は高くなります。最低3年以上の経験を積むことで、ファーム出身者としてのスキル・知識・実績をしっかり身につけるのがおすすめです。クライアントがなぜフリーコンサルに関して高額の単価を支払うかというと、それはフリーコンサルのコンサルとしてのソフトスキルであったり、これまでの経験や知見を買っていると言えます。
よってこの観点で考えると少なくとも3年以上の経験がないと、クライアントとしては高額の単価を支払って外部の人員を入れる必要がなくなると言えます。
職務経歴書の整備
エージェントを利用する場合も、直接営業する場合も、職務経歴書は必須です。これまでの担当プロジェクト、役割、成果を具体的にまとめ、専門的な知識や得意領域を明確に示すことで、自分に合った案件を獲得しやすくなります。
個人事業主か法人化か
最初は個人事業主として開業し、後々法人化するという方法も一般的です。税制面や社会的信用度の点から法人化を選ぶ人もいますが、設立や維持に手間がかかるデメリットもあります。
また、住宅ローンなどの審査を考えると、フリーになる前に契約を済ませておく方がスムーズという声も多いです。
フリーコンサルに向いている人・向いていない人

フリーコンサルに向いている人
フリーコンサルに向いている人は、やはりコンサルティングファーム時代と変わらずパフォーマンスを発揮できる人かと思います。結局やるプロジェクトの内容としては同様なので、これまでと同じようにクライアントに対してバリュー出せるかどうかと言うとこが非常に大きなポイントです。またクライアントはこれまでの経験知見を買うと言うところから考えてみても、やはり専門性が高い方、経歴にエッチが立っている方は非常に発注の確度は高くなるかと思います。
- コンサルティングファーム時代と変わらぬパフォーマンスを発揮できる人
- バリューを出し続けられる継続力・責任感
- 自立して動ける人
- 課題抽出から解決策の提案、顧客折衝まで、一連のプロセスを自走できるコミュニケーション力
- 一定の専門領域や豊富な知識を持つ人
- 特定業界(エネルギー、金融、製造業など)や機能領域(M&A、PMO、IT導入)への深い理解
フリーコンサルに向いていない人
一方で、フリーコンサルに向いていない人と言うのは、受け身の姿勢で仕事をしてきた人、能動的にバリューを出そうと言う動きをして来なかった人、また金銭的にリスクを超えない人と言うのは、フリーコンサルは働き方として不安定な側面をもちろんあるので、その点で関してもあまり向いていないかもしれません。
- 受け身の姿勢で仕事をしてきた人
- フリーランスでは、自分で顧客をコントロールしながら業務を進めることが求められます。
- ネットワーク作りや営業活動が苦手な人
- 案件獲得のためには、多少なりとも営業力・コミュニケーション力が必要です。
- 資金的リスクを取りたくない人
- 稼働が途切れれば収入がなくなる可能性があるので、リスクを許容できない場合は向いていないかもしれません。
まとめ

フリーコンサルは、コンサルティングファームで培ったノウハウや実績を活かしながら、自分のペースや得意分野に合わせて働ける魅力的な選択肢です。一方で、案件獲得や稼働管理、税務処理など、自己管理が必須であることを忘れてはいけません。
- メリット:報酬の高さや働き方の柔軟性が魅力だが、稼働しなければ収入が得られないリスクもある
- コンサルティングファームでの3年以上の経験や専門性があるほど案件は獲得しやすくなる
- エージェントや人脈を活用することで、自分に合った案件を見つけることが可能
- 個人事業主か法人化か、ローンや信用力の問題など事前に検討すべき点も多い
今後、フリーコンサルとして独立を考えている方は、まずはファーム時代のスキルやネットワークを十分に活かしつつ、案件獲得や働き方のイメージを具体化してみるとよいでしょう。